|
|
|
お問い合わせ
|
|
| 日 付 | 更新履歴・お知らせ・独り言・ぶつぶつ…のようなもの |
| 24/12/10 | ●インドの大魔王「お笑い神話12月号:霧が覆い隠すシッキム王国の“神秘”(2)」をアップしました。 |
|
|
|
24/12/05 司馬遼太郎 著 |
●以前、兵庫県赤穂市の坂越港からすぐ近くの、小高い山の上にある大避神社のことを書いた(20.11.25)。「大避(おおさけ)」だから大波からの避難場所になっていたのだろうとしるした。だけど、これが全く違った。不思議な来歴をもつ神社だった。司馬遼太郎「兜率天の巡礼」(『ペルシャの幻術師』所収、文春文庫、2001)は、その来歴をモチーフに語られる短編小説である。それによると、「大避」は「大闢」が誤記されたものという。その大闢(だいびゃく)の意味するところはなんと「ダビデ」であった。旧約に登場するあのダビデである。境内には「いすらい井戸」があり、その「いすらい」は「イスラエル」のこと。ダビデを坂越の地に祀ったのは、異端とされたネストリウス派キリスト教徒(景教)のユダヤ人であった。かれら渡来人たちはのちに「秦氏」と呼ばれるようになる。「秦」は中国で「ローマ(東ローマ帝国)」を意味する「大秦(だいしん・たいしん)」に由来するのだそう。その秦氏が京の都に本拠地として築いたところが「太秦(うずまさ)」。そしてそこにあるのが「大酒神社」。大闢→大避→大酒、というわけ。境内には大避神社と同じように「やすらい井戸」が残る。フランシスコ・ザビエル以前に古代キリスト教が日本に伝来していたということになる。この説を唱えたのは、エリザベス・アンナ・ゴルドンという英国人の宗教研究家。明治末から日本で過ごし、1925年(大正14)京都で亡くなった。 |
|
|
|
24/11/17 原作・絵 :栗原エミ |
●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 ・音のない世界 葛藤と挑戦 デフ卓球金 上田萌さん「健常者とのかけ橋に」 ●『明子(めいこ) 被爆者である母のこと-南方特別留学生との友情-』(原作・絵 栗原エミ、発行 シフトプロジェクト、2024年)という絵本を知った。著者栗原エミの母親である栗原明子は学徒動員で働いていた東洋工業で「8月6日」を迎えた。市内にあった実家のあとを訪ね歩くが跡形もなく「異様な静寂があるばかり」。翌7日から1週間、広島文理科大学のキャンパスで8人の留学生と助け合いながら野宿をして過ごす。留学生のバイオリンの演奏があったり、みんなで歌を歌ったり。「被爆したものどうしの集まりとは思えない心なごむ夜」。明子にとってそこでの経験が「生きていく希望をもらった一生忘れられない宝物」となった……。 明子さんの、この「1週間」のことは、小舎刊『南方特別留学生ラザクの「戦後」』(宇高雄志著)で「文理科大学の星空」(72-76頁)という見出しで紹介されている。明子さんの手記や著者との手紙のやりとりなどから再現したもの。書名にもなっている「ラザク」さんは、マレーからの留学生で、戦後は祖国マレーシアでマハティール首相が打ち出したルックイースト政策のもと日本語教育に尽力し日マの架け橋となった人物だ。明子さんが大学キャンパスで野宿をともにした8人の留学生のなかの一人である。 この絵本のことを教えてくださったのは愛原惇士郎氏。愛原氏は著者宇高氏の恩師にあたり、しかも、マレーシアから日本へ留学する工学系の学生たちにむけて予備的な教育(日本語、数学、物理など)を実施する、マレー工科大学に付属する機関で教鞭も執られていた(愛原氏のマレーシアでの活動は本書168-169頁に紹介されている)。そして、ほんとにほんとに縁とは不思議なものなのだが、愛原氏はわが母(今年卒寿を迎えた)の小学校時代の仲良しグループ(つまり80年をゆうに超える同窓!)のメンバーで、いまも年に数回食事会や小旅行が恒例になっている。つい先日も一泊二日の旅行があり、母がこの絵本を愛原氏から託かってきたという次第なのだ。愛原先生、ありがとうございます。 ところで「明子」というお名前を「めいこ」と読むのはこの絵本で初めて知った。5月生まれゆえに「May」(メイ)と、医師であったご尊父が命名されたとか。編集者としては、きちんと調べて「めいこ」とルビを振るぐらいのことができなきゃいけなかった……。反省してます。 |
|
|
|
| 24/11/04 | ●第13回「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(その10)をアップしました。この第13回をもちまして「鶴見良行の世界」編は終了となります。ご愛読ありがとうございました。 ●インドの大魔王「お笑い神話11月号:霧が覆い隠すシッキム王国の“神秘”(1)」をアップしました。 |
|
|
|
| 24/10/21 | ●インドの大魔王「お笑い神話(10月号)」をアップしました。 ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 ・「敗北」を糧に 問われる真価 張本智和を強くする新たな覚悟 |
|
|
|
| 24/10/09 | ●第12回「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(その9)をアップしました。 |
|
|
|
| 24/09/26 | ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 「ミルコが闘い続けた理由『クロアチアは血の中で生まれたんだ』」 |
|
|
|
24/09/23 タミル語入門 |
●小舎刊『タミル語入門』を私どもの通販サイト(BASE)からご注文された方へ。 このたびの増刷をお待ちいただいていた方が当方の予想をはるかに超えていらっしゃったことに驚いております。まことにありがたく厚く御礼申しあげます。ただ、ひとり出版社故に出荷の態勢が不十分で、受注・発送等のご返信・ご案内が遅れ気味になっておりますこと、ふかくお詫び申しあげます。本日(23日)までにご注文いただいている方へは、今週末28日(土)までにお手元にお届けできるよう進めておりますので、ご理解を賜りたくよろしくお願い申しあげます。なお書店経由でのご注文も可能です。時間はかかりますがご利用いただければ幸いです。またamazonのサイトでの販売も「品切」から「取扱 可」へのステータスの変更を申請しておりますが、対応が遅れ気味でいまだ情報が更新されていないようです。ご迷惑をおかけしております。 |
|
|
|
| 24/09/12 | ●第11回「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(その8)をアップしました。 ●インドの大魔王「お笑い神話(9月号)」をアップしました。 |
|
|
|
| 24/08/25 | ●小舎刊行の『タミル語入門』についてのお知らせです。近々第4刷の印刷に入る予定です。2019年にほぼ品切れ状態となり、20年春からはコロナ禍に見舞われ、その影響でしょうか、いわゆる「海外モノ」の需要が一気に冷え込みました。そうした状況が続いたこともあり、この4年間、品切れ状態のままになっておりました。コロナ禍もほぼ終息となってきた今年あたりから、ありがたいことに在庫のお問い合せをいただくことが増えてまいりました。ということで、遅ればせではありますが、増刷に入ります。9月下旬あたりに出来上がる予定です。よろしくお願いいたします。 |
|
|
|
| 24/08/17 | ●第10回「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(その7)をアップしました。 ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 「ピンポン外交官 五輪に抱いた夢 国旗・国歌、国籍も問わぬ姿に」 |
|
|
|
| 24/08/04 | ●インドの大魔王「お笑い神話(8月号)」をアップしました。 |
|
|
|
| 24/07/24 | ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 「パラ陸上の歴史を変えた情熱『義足で走る』 願いかなえた義肢装具士」 ●インドの大魔王「お笑い神話(7月号)」をアップしました。 |
|
|
|
| 24/07/12 | ●第9回「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(その6)をアップしました。 |
|
|
|
| 24/07/03 | ●「大阪自由大学通信7月号」が届きましたのでアップいたします。 |
|
|
|
| 24/06/29 | ●大魔王こと大麻豊氏より「ヨガ展」(インド政府主催)の案内がありました。 ・とき:7月3日〜6日 ・ところ:大阪府立中之島図書館 ・参加費は無料です。詳しくは、こちらのPDF(フライヤー)を参照ください。 |
|
|
|
| 24/06/23 |
●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 「キング牧師と共有した五輪精神 アトランタ五輪聖火ランナー バーバラさんの願い」 |
|
|
|
24/06/15 ドリームタイム |
●「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』大津和子と鶴見良行(5)をアップしました。 ●藤工作所の藤原武志さんより最新刊『ドリームタイム 野外劇団楽市楽座 明日を占う投げ銭の旅』(佐野キリコ・著)をお送りいただいた。楽市楽座という家族劇団(著者キリコ夫妻とその娘・萌さんと、後にその夫の4人)が全国を巡回する「旅芸人の記録」。すべてが手作りの野外劇で観客からの投げ銭だけが頼りの、その無謀とも思える役者魂を貫く。著者のオプティミスチックなバイタリティがあらゆる困難をばったばったとなぎ倒し、すべてが予定された「必然」に収めていく。学校にも通わず、9歳から旅芸人となった娘の萌さんは17歳で伴侶を得、一緒に舞台に立つ。彼女の文章が本書の巻末に収録されている。これがとってもいい。この一文で、キリコさんのテンポのいい、15年にもなんなんとする「珍道中」がぴしゃりと着地したように感じた。お求めは藤工作所の販売窓口へ。 |
|
|
|
| 24/06/08 | ●インドの大魔王「お笑い神話(6月号)」をアップしました。 ●大魔王こと大麻豊氏より国際ヨガDAYの案内がありました。来る6月23日(日)、万博公園(太陽の塔横)で開催されます。詳しくはこちらのフライヤーで。また7月3日〜6日には大阪・中之島図書館でヨガ展とワークショップが行われます。ともにインド政府主催で、参加費無料です。 |
|
|
|
24/06/02 |
●どこで「カフカ」を刷り込まれていたのだろう。特別にカフカの愛読者でもないのに、5月に出た『決定版カフカ短編集』(新潮文庫)を読んだ。無自覚に手にしたものと思っていたのだが、そうでもなかったかもしれない。なんとなれ、今年はカフカ没後100年にあたるらしいのだから。本書巻末に収められた「編者解説」にこのアンソロジーを組んだ頭木(かしらぎ)弘樹氏が「個人的な思い」という見出しでご自身のことをしるした、次のような内容の下りがある。 「20歳で難病になり、13年間の闘病生活」を送っていた、本書の底本となった『決定版カフカ全集』をかたわらに置いて事あるごとに読んでいた。「全巻それぞれ100回以上は読んでいると思う」と。この全集は全12巻、うち半分が日記と書簡らしいが、それらを100回以上!というわけだ。この「100回」もそうだが、20歳から13年間という長い闘病生活をさらりと言ってのける文章に既視感があった。ああ、この人のコラムを最近新聞で読んだぞとふと思いだしたのだった。 「12年目の電話」(日経新聞「交遊抄」2024.3.9)と題したコラムだ。 内容を要約すると──。大学3年の20歳の時から病に伏していたが、13年目に手術をして普通の生活が可能に。入院中耽読していたカフカの翻訳と評論の本を出す。好評であったが出版社が倒産。本は差し押さえに。でも本を出したんだからどこかからまた依頼があるだろうと思っていた。が「10年待っても電話はなかった」。職歴のない無職の人間に社会は冷たかった。クレジットカードも作れなかった。しかし「12年目に電話があった!」「編集者の品川亮さん」という方からで『絶望名人カフカの人生論』という本を二人三脚で出版。それがきっかけとなり以後、「継続的に本を出せるようになった」と。 この記事を読んだ当時、執筆者の頭木氏のお名前もバックグランドも何も知らなかった。ただ、10年20年の不遇を乾いたタッチでしるし、10数年目にしてようやく新たな一歩を踏み出した、そうした雌伏の時期を声高にかこつでもなく、淡々と振り返る時間感覚がとても印象的でスクラップしていた。この記事が私のどこかに「カフカ」を刷り込んでいたようだ。 |
|
|
|
| 24/05/23 | ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 「神様に好かれるやつは、悪魔にも」マイク・タイソンの栄光と凋落 |
|
|
|
| 24/05/19 | ●文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(4)をアップしました。 |
|
|
|
| 24/05/13 | ●ふだんあまり使っていないバックアップ用のパソコンを久しぶりに立ち上げたところ、消失してしまっていたホームページのファイルの断片がディスクに残されていたのを発見! ありがたし。というわけでWhat's NEWの一部(2023年4月-7月)を復元しましたのでお知らせします。 ●おそらく5回目ぐらいになるのだろうか、4月からNHKラジオ「アラビア語講座」を聴いている。「NHKらじる・らじる」のソフトがあるので聞き逃しても1週間はネット経由でいつでも再生できる。便利になった。以前にも書いたが、当番組は2005年4月から9月に放送されたもの。それを繰り返し繰り返し放送している。なんと今回で20周年というわけだ。講師の榮谷温子先生も20年ぶん年をとられたということになる。ともあれ、私的には、学んでは忘れ、忘れては学ぶの、進歩なき無限ループ状態に安住しているので、何周目であろうと鮮度高く番組に接せられている。だから……問題はないのだ。 |
|
|
|
| 24/05/02 | ●文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(3)をアップしました。 ●インドの大魔王「お笑い神話(5月号)」をアップしました。 ●大阪自由大学通信(5月号)をアップしました。 |
|
|
|
| 24/04/26 | ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)をリンクします。 「輝きの隣にいたからこそ 卓球界を陰で支えた男の矜持」 |
|
|
|
| 24/04/12 | ●第5回 文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』(2)をアップいたしました。 |
|
|
|
24/04/06 書いてはいけない  日航123便 墜落の新事実 |
●日経新聞夕刊「文化欄」(2024.4.4)に、森永卓郎『書いてはいけない』(三五館シンシャ、2024)の書評が掲載されていた。財務省の主導する「緊縮財政(財政均衡主義)・増税路線」を徹底して批判してきた森永氏の著作群は、ある種の忖度が働いているのか、大手メディアで取り上げられることはこれまでほとんどなかった。それが、財務省・経団連の広報紙(?)ともいえる日経新聞に登場したものだからちょっと驚いている。前著『ザイム真理教』(三五館シンシャ、2023)は、タイトルが語るように、財務省の言説に毒された多くの国民が巨大カルト化してしまった状況に警鐘を鳴らし、財務省が声高に唱える財政破綻論の「ウソ」を暴いていく内容である。しかしこのたびの『書いてはいけない』はそれ以上に、財務省云々の範疇をはるかに飛び越えて、国家レベル的に「不都合な真実」を衆人環視のもとへと引きずり出す。とくに1985年の日本航空123便墜落事故と、日本経済との関係に言及している下りは衝撃的だ。日航機123便の事故原因を追及している青山透子氏の一連の著作もほとんどの大手メディアは黙殺しているが、その青山氏の主張するところの、「ほんとうの事故原因」の隠蔽(『日航123便 墜落の新事実』河出文庫、2020)が、森永氏の見立てでは、その後の日本経済凋落の禍根となっていった。日米構造会議という対米全面服従を一方的に呑まされる、会議とは名ばかりの「場」が設けられ、さらには「年次改革要望書」という、「要望」とは名ばかりの、米国政府から日本政府へ「命令書」が突きつけられ、米国に都合のいい構造改革を押しつけられる。日本政府の米国政府への隷属化路線が決定的に固定化されていく。日経としては、大いに忖度して、触らぬ神に祟りなしときめこんでしかるべき内容のものだ。評者(経営学者・入山章栄氏)の“力量”によるものか、あるいはメディアの風向きがすこし変わってきているのだろうか……。 |
|
|
|
| 24/04/02 | ●インドの大魔王「お笑い神話(4月号)」をアップしました。 ●トラベルミトラの大麻豊氏より「インド舞踊」のご案内です。鳥取でのイベントです。 「インド舞踊へのいざない」(フライヤー) インド北東部マニプル州より来日! マニプリ古典舞踊団と 日本で活躍する南インド古典舞踊団によるインド舞踊の祭典 ・日時:4月16日(火)18:30開演(18:00開場・20:30頃 終演予定・休憩あり) ・会場:鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) ・主催:在大阪・神戸インド総領事館 ・共催:鳥取県 ・入場無料です。 ・申し込み方法:下記URLから。 https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11309 |
|
|
|
24/03/27 『人間失格・桜桃』 |
●アラビア語のレッスンで太宰治の「人間失格」を読んでいくことになった。シリアの文学者で詩人、東大の非常勤講師をされているムハンマド・オダイマという方によるアラビア語への翻訳版。とりあえず事前準備に日本語で目を通しておこうと、原著(『人間失格・桜桃』角川文庫・1950)を本箱から探し出してきてほぼ半世紀ぶりに読んだ。どんな内容だったのか忘却の彼方のことである。しかし、導入部分の数ページでなんとも嫌な気分に襲われ、さらに読み進んでいくにつれ不快感はいや増しに。投げ出したくなる気分を押さえ込みながらの苦行であった。若かりし頃どういうふうな思いでこれを読んでいたのだろう。「ブンガクだ!」と感じ入っていたのだろうか。還暦を過ぎた、老境の身にはただただ鬱陶しい物語であったとしか言いようがない。「恥の多い生涯を送って来ました」なんて、そんな独白をえんえんと聞かされたところで「みんなそうなんよ!」と呟きたい。深夜、ふと目が覚めて、脈絡もなしに昼間のあれやこれやを思い出し、その恥ずかしきわが言動に、貧相なわが振る舞いに、思わずギャーッ!と奇声をあげることしばしば。あちらこちらの寝間は奇声であふれかえっているはずだ(たぶん)。「唐詩選」にある「人生別離足ル(人生には別れがいっぱい)」に倣えば、「人生慚愧足ル」だ。井伏鱒二の「サヨナラダケガ人生ダ」に倣えば、「赤ッパジダケガ人生ダ」なのだ。アラビア語版の書名はベタで直訳すると「…そして、もはや彼は男ではない」であった。ただこれは英語版タイトルの「No Longer Human」からの重訳っぽい感じ。Humanではなく「男(ラジュル)」と表現されるあたりがアラビア語圏ならでは語法か。ともあれ、これを教材にレッスンは始まったのだが、「男じゃない」だの、「人間じゃない」だのと、数々の「失格」の烙印にわが身は打ちひしがれて、先生も私もともにテンションがいまいち上がらずじまい。次回からはテキストが変わることになった。よかった。 |
|
|
|
| 24/03/16 | ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)第8回をリンクします。 「アリとは違う伝説になる」“悪魔王子”ナジーム・ハメドが抱いた夢 |
|
|
|
| 24/03/08 | ●第4回 文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」『バナナと日本人』をアップいたしました。 |
|
|
|
| 24/03/02 | ●大阪自由大学通信(3月号)をアップしました。 ●インドの大魔王「お笑い神話(3月号)」をアップしました。 ●「スポーツ森羅万象」(城島充/サンケイ夕刊)第7回をリンクします。 「葛西紀明が飛び続ける理由 故郷の原風景と亡き母のメッセージ」 |
|
|
|
| 24/02/19 | ●第3回『文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」』をアップいたしました。 |
|
|
|
| 24/02/07 | ●インドの大魔王「お笑い神話(2月号)」をアップしました。 ●ちょいヨミ ななめヨミ 本のはなし『ガザとは何か』をアップしました。 |
|
|
|
| 24/02/03 | ●大阪自由大学通信(2月号)をアップしました。 ●城島充氏による「サンケイ」(夕刊)紙上での「スポーツ森羅万象」好評連載中です。 これまでの記事を下記にリンクして一覧にしますのでどうぞご一読を。 第1回:「大阪五輪」恩人が描いた夢 万博会場は「海上五輪」の舞台だった 第2回:知らなかった 水谷隼16歳の覚悟 「僕はすべてを捨ててドイツに来た」 第3回:120%、沖縄のために戦った」ヒーローの実像にふれて生まれた葛藤 具志堅用高 第4回:「武蔵野のローレライ」上原久枝さん「世界のオギムラ」支えた献身 第5回:朝青龍「私が日本人だったら…」横綱の品格とは「反逆児」の葛藤 第6回:岡山のジム初の世界王者誕生 ローカルジムで紡がれた拳の絆 |
|
|
|
| 24/01/23 | ●第2回『文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」』をアップいたしました。 |
|
|
|
| 24/01/09 | ●インドの大魔王「お笑い神話(1月号)」をアップしました。 ●大阪自由大学通信(1月号)をアップしました。 ●ちょいヨミ ななめヨミ 本のはなし『ヴェネチィアの宿』をアップしました。 |
|
|
|
| 24/01/04 | ●本年もご愛顧のほどお願い申しあげます。能登大震災、日航機炎上と大きな惨事に見舞われ、たいへんな幕開けとなりました。被災された方々にお見舞い申しあげます。 ●『文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」』(庄野護著)の連載が始まります。 |
|
|
|
| 23/12/30 | ●ぎりぎりになってやってしまった!このページ・ファイルを編集してるところで知らないうちに11月以前のデータのほとんどを破損・消失してしまい、間の悪いことにそのことに気づかないままWebサーバー上にあるファイルに上書きしてしまった。というわけで2023年4月から11月上旬までの内容はなくなってしまいました。ご諒承ください。「こまった、こまった」と嘆いていたら家人から「誰も困っていないはずよ」と断言され、たしかにそういうものかなとも思い直している。うん、たしかに困らない。でも万一気になる方がいらっしゃれば秋に刊行いたしました『哀愁のコロフォン』に7月ごろまでのものは一部収録しておりますのでご購読いただければ幸いです。 ●今年も何かとお世話になりありがとうございました。それではよいお年を! |
|
|
|
| 23/12/28 | ●昨晩発信の元(はじめ)正章牧師からの月刊「益田っこ通信」に添えられたメールの一文に声を失った。大橋愛由等氏が25日朝方、脳梗塞で亡くなったという。68歳。病気とは無縁の、エネルギッシュな印象しかない。信じられない思いだ。「津川雅彦ばりの美男子で、神戸のダダイスト、風狂の歌人……、スペイン料理カルメンの店主にして、出版社まろうど社社主のほか、彼の足跡を挙げれば、他にもいろんなことで活躍していた」(元氏)。そう、ほんとうに多才な人だった。かつて私がかかわっていた「大阪編集教室」という学校ではライティングの講師を2002年から10数年間引き受けてもらった。直近でお会いしたのは、一昨年の夏、元牧師の帰省に合わせて催された、阪急六甲の中華料理屋さんでの酒席であった。いつもの談論風発ぶりだった。たしか御尊父が在籍されていた、満洲国の建国大学の話題であったように記憶する。今夏も元氏と大橋氏の「カルメン」で一献の予定であったが、これは事情あって流れてしまった。今となって思えば残念なことであった。ご冥福をお祈りします。 |
|
|
|
| 23/12/04 | ●インドの大魔王「お笑い神話(12月号)紅葉の小径を独り歩け」をアップしました。 |
|
|
|
| 23/12/01 | ●大阪自由大学通信(12月号)をアップしました。 |
|
|
|
23/11/28 |
●神戸サンボーホールという、貿易センタービル横のイベントホールで例年実施されていた古本市(去年は中止だった)が、今年は場所を変えて、「第一回えべっさん古本まつり」と銘打って西宮神社の境内で開催された(11月23日〜27日)。死ぬまでかかっても読み切れないほどの積ん読状態にあり、もうそろそろ落ち着いて一意専心読むほうに注力すべき年齢なのに「古本市」と聞けばそわそわしてしまう。批評家の若松英輔氏が愛書家を「読書家・購書家・蔵書家」に分類して論じている記事(日経、2023.10.21)を目にしたが、そこで使われていた「購書家」という呼称が印象的であった。ともあれ、初日の23日、えべっさんに向かった。20店舗あまりの出店で、お天気もよく、サンボーホール時代よりもお客さんも多くて賑やかな印象であった。その夜の主催者のSNSには、初日のまとめとして「大盛況であった」「新たにかなり補充した」という文言が並んでいた。そうか、新たな補充がなされたのか……。であればもういっぺん行ってみようか、ということで25日、再びえべっさんへ。ふつうだったら、大人しくシンボーする。さすがにもういっぺんとはならない。ならないのだが、初日に買った、徳永康元『ブダペスト日記』(新宿書房、2004)に影響されてしまったのだと思う。著者の徳永康元氏(1912-2003)は、戦前にハンガリーに留学されていた言語学者。文化人類学者の山口昌男氏は、著者のことを、酒の世界の酒仙になぞらえて、本の世界の「書仙」と呼んだ(坪内祐三「徳永康元さんの思い出」本書所収)。高名な愛書家であり、国内外の古書事情に精通したエキスパート。その著者と、先の山口氏との対談(「古本漁りはパフォーマンス」)が本書に収録されており、そこに徳永氏のつぎのような発言があった。「(略)年をとると、本集めは、かえってやめちゃいけないといいますね。九十になっても、死ぬ二、三日前まで買ってたという人が、幾人もいますよ。そういう人は、頭がちゃんとしているね。やめちゃった人はだめだ。(略)」だって。これでシンボーがきかなくなってしまったか……。 |
|
|
|
| 23/11/20 | ●ノンフィクション作家の城島充氏より古巣の「サンケイ」(夕刊)で連載(月2回)をはじめた旨の案内をもらった。第1回は〈「大阪五輪」恩人が描いた夢 万博会場は「海上五輪」の舞台だった〉。2025年大阪・関西万博に向けて工事が進められている、ここんところ何かと話題の人工島(夢洲)は、かつて2008年開催の夏季五輪の会場予定地であった。城島氏自身の人生の岐路において多大な影響を及ぼした、今は亡き恩人(当時の大阪五輪推進部長)の思い出とともに、その招致活動の舞台裏が語られる(予定?)。四半世紀前、「大阪五輪」が云々されていたことは私の記憶からはとっくに消えてしまっていた。「かつて同じ人工島にまったく違う大阪の未来図を描いた人物がいたことを一人でも多くの人に伝えたい」と城島氏はしるしている。 |
|
|
|
|
2023年7月下旬から11月中旬までのデータを消失しました。
|
|
|
|
|
| 23/07/17 |
●大阪自由大学の安村氏より「なにわ古代史」の第6回目講座として「高槻・今城塚古墳 継体天皇陵の背景 なぜ淀川水系に築造されたのか」の案内が届いています。9月28日(木)午後2時から大阪市中央公会堂大会議室です。詳しくはこちらのフライヤーをご覧ください。
●村上春樹「納屋を焼く」を教材にアラビア語のレッスンを受けていることは以前しるした。牛歩のごとく遅々として進んでいないのだが、このアラビア語版の翻訳の自由奔放さに驚いている。原文に登場する「彼女」の描き方がじつに“悪意”に満ちているのだ。原作では、どちらかといえば中性的で、さっぱりした性格の、現代的な女性が、アラビア語版ではふしだらで厚かましくて不道徳な女性として描かれる。「我々は食事をしてからバーに行ったり、ジャズ・クラブに行ったり、夜の散歩をしたりした」という日本語原文が、なぜか、「(酒場では)私のほうが食事や飲み物の代金を支払っていた。いやむしろ彼女はいつもお金がなかったし、いよいよ食事代に困ると彼女のほうから私に連絡してきた。その時の彼女のがつがつと食べる量ときたら信じられないほどだった」(アラビア語)ってな具合になる。あきらかに翻訳者の偏見が、原文には見あたらない、あらたな文章を作りだしている。これはほんの一例で、いたるところで彼女のキャラが歪んで描かれる。逐語訳である必要はないけれど、それでもこれはやり過ぎだ。翻訳の域を超えている。とはいいながら、この突飛な翻訳にレッスン中は大いに笑わせてもらっているんだけど。さて、最近テレビのニュース番組などで流される、インバウンドでやって来た外国人観光客へのインタビューを眺めていて、彼らが発するコメントが日本語の吹き替え音声になっていたりすると、本当にそういう内容をそのようなテンションでしゃべっているのかなと疑問に思うことがある。吹き替えではなく字幕スーパにしてもともとの音声も流すべきだと思うのだ。まあ観光客の感想あたりでは致命的な問題なんて起きそうにはなさそうだけれど、とりあえず報道番組としてのちのち検証ができる状態にはしておくべきだろう。以前、NHKのウクライナ避難者(高齢の女性)へのインタビュー(2022.4.10放送)で「今は大変だけど、平和になるように祈っている」という字幕であったものが、実際の発言は「私たちが勝つと願っています。ウクライナに栄光あれ」だった。だいぶニュアンスが違っている。ロシア語・ウクライナ語だからばれないと思っていたのかな。もともとの音声が流れていたから指摘する人がいたわけだけど、こういうことってけっこうありそうな気がする。 |
|
|
|
23/07/09 とくしま世界ゴハン |
●インドの大魔王「お笑い神話(7月号)をアップしました。
●大阪自由大学通信(7月号)をアップしました。 ●徳島在住のS氏の案内で「花(か)んらん」(徳島市)というお好み焼き屋さんへ行った。不思議なお店で、メインメニューは当然「お好み焼き」であるのだが、女主人の夫であるスリランカ出身のラリスさんが提供するスリランカ料理「アーユルヴェーダプレート」がもう一つの人気メニューになっている。『とくしま世界ゴハン』(メディコム、2022)というガイドブックには、「スパイスの特徴や役割をサイエンスの視点」から考えて、免疫力を高めてくれる健康にいい料理を心がけているとのラリスさんのひと言が紹介されている。この「サイエンスの視点」にはもう少し説明が必要だろう。というのは、ラリスさん、正真正銘のドクターなのであった。キャンディにある国立ペラデニア大学を卒業後、恩師のすすめで徳島県の鳴門教育大学大学院に進み、化学の修士号を修め、その後徳島大学大学院に留学し病理学の博士号を取得している。そして渡米。アメリカではジストロフィーやHIVなどの難病研究に10年間従事してきた経歴の持ち主。奥さんいわく、「これまでは話し相手といえば顕微鏡の向こうにある細胞しかなかったのよ」。今では客商売にも慣れて、「キャベツを切るスピードは誰にも負けないよ」とラリスさんがカウンターの向こうで笑っている。月に一度、「スリランカナイト」と題してビュッフェ形式でスリランカ料理を堪能できる一夜がある。いつかはこちらも訪れてみたい。なお、店名の「かんらん」とは「キャベツ」の意。中国語で「葉牡丹」を意味する「甘藍」という漢字が当てられる。 |
|
|
|
23/07/03 『火蛾』 |
●「23年後の復刊」という見出しがつけられた、古泉迦十『火蛾(ひが)』(講談社、2000)の文庫化の記事(朝日新聞、2023.6.8)が目にとまった。イスラム神秘主義をモチーフに修行者たちのあいだで繰り広げられる連続殺人を描いたミステリー小説。スン二派ともシーア派とも一線を画した、神との合一・一体化を究極の境地としてめざす、正統派イスラムからは異端視される神秘主義(スーフィズム)。そのスーフィズムの“極北”ともいえるウワイス派がその舞台設定だ。言葉そのものをも「偶像」として否定し、その教えは霊の交信をもって継承されるともいわれる異端中の異端。イスラムの、しかもスーフィズムという、当時としては多くの人にとってほとんど馴染みのない世界を語る、かなり異色の作品といえよう。講談社が主催するミステリ部門のメフィスト賞第17回受賞作品(2000年)であるが、さすがに他の受賞作品と比べて部数の伸びが鈍かったようで、文庫化が見送られたという経緯があったようだ。わたしもメフィスト賞発表後の、十数年あとに古本で手に取った次第で、その作品の特殊な内容もさることながら、著者古泉迦十が当該作品以外の作品を発表することもなく、斯界からは消えてしまったように見受けられ、しかも著者プロフィールは「1975年生まれ」としるされるだけで、その匿名性に強烈な印象を持ち続けていた。記事によると第2作目『崑崙奴』を執筆中とある。少しずつ著者のことも明らかになってくるのかもしれない。
|
|
|
|
| 23/06/16 |
●鶴見良行私論appendix「鶴見良行の「アメリカの越え方」(2)」をアップしました。
|
|
|
|
23/06/06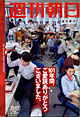 終刊号 |
●インドの大魔王「お笑い神話(6月号)をアップしました。
●『週刊朝日』の終刊号(2023.6.9)を記念に買った。雑誌を買うのはほんとに久しぶり。雑誌が元気な1980年代は毎年何誌も創刊されていたもので、そんな創刊号を買うのが楽しみだった。「ダカーポ」や「フォーカス」「ナンバー」などの創刊号が手元に残っている。40年近くたってから眺めてみるとその時代性がくっきりと感じ取れてじゅうぶんに興味深い。しかし終刊号というのはパッとしないものだなあというのがこのたびの感想。これまでの寄稿者がオマージュをささげあうといった内容でちょっとみっともない。「週刊朝日には品位があった」って、何それ?「昔はよかった」的なセンチメンタルな言辞にあふれている。ジャーナリズムが機能しない今の世を嘆くべきだろう。「新聞社系の週刊誌の時代はだいぶ前に終わっていた」とのコメントには納得。 |
|
|
|
| 23/05/26 |
●ひと月ほど前からトップページの「リンク」コーナーに「小室直樹文献目録」というサイトを掲載している。小室直樹(1932-2010)による著作物(書籍、新聞、雑誌、冊子、映像、音声など)を網羅した「文献目録」と、「小室直樹」に言及している第三者の手になる著作物をリスト化した「関連文献目録」など、これまでこの世に存在している「小室直樹」にかかわるテキスト・映像�・音声のすべてを根こそぎ集積すべく運営されている情報サイトである。運営者は『評伝小室直樹』(ミネルヴァ書房、2018)の著者村上篤直氏。かつてひょんなことから村上氏より連絡をいただき、私どもの手元にあった「小室資料」(整理番号1979009)を寄贈した経緯がある(詳細は「What's NEW! 2018.9.16」を参照ください)。「小室直樹」の、たんなる一愛読者でしかない私がこうした情報サイトへ微力ながらも貢献できたことはとてもうれしいことだった。以来、ウン十年前に出版された、関連しそうな本や雑誌などを本棚から取り出して、そこに「小室直樹」の名を発見すると、これはリストアップされてるのかな?と当サイトで検索したものだった。果たしてとっくの昔にちゃあんと捕捉されている。残念。ところが先月末に発見したのだ!『第49回日本社会学会大会報告要旨』(1976)という一冊。くるみ製本の、背文字もない冊子なので棚ざしでは内容がわからなかったのだ。この第49回の学会は、私が入学した大学で開催されていた。しかも入学した同じ年の秋の実施である。もちろん参加した記憶もなく、なぜこの冊子を持っていたのかも、半世紀近くたった今となっては全くの記憶がないのであるが、ひょっとしたら事務課の窓口にでも山積みにされていたものをもらってきたのだろうか。ともあれ、その9頁から10頁にかけて小室直樹による発表要旨が小室氏の直筆で記されていたのだった。早速村上氏にメールでその旨をお知らせし寄贈した。「これはすごいです!! まさか、このような文献が未発見のまま残されていたとは」と大いに驚いたいただけた。してやったり! とってもうれしい! 整理番号1976007が付与された。ところで拙著『活字の厨房』(2018)も「関連目録」の一つとして掲載されている。整理番号2018121だ。こちらは村上氏にお送りして無理強いしたような感じ……ではあるが、ともあれこれまたうれしい。
|
|
|
|
23/05/12 村上春樹 著 |
●鶴見良行私論appendix「鶴見良行の「アメリカの越え方」(1)」をアップしました。
●今年も4月29日から5月の連休中、神戸・元町映画館で「イスラーム映画祭(第8回)」が開催された。今年の目玉はなんといってもパレスチナの作家ガッサーン・カナファーニー原作の「太陽の男たち」(1972年)。劇場初公開だそう。上映3時間前に足を運んだが、すでに売り切れ!であった。なんとなく予感はあったが、がっかり。そういえば、3年前に上映された「ザ�・メッセージ」(アラビア語版は「アッ・リサーラ」)も何時間も前に完売していた。もともとはハリウッド映画であったものをアラブ人俳優に入れ替えて製作されたリメイク版。「幻のアラビア語版」といわれ日本発上映であった。このときはイスラーム映画で満席になるなんてことがあるのか!と心底驚いたものだったが、最近は「やっぱり」という感じになってきた。だいぶ「イスラーム映画祭」も人口に膾炙してきたか。ともあれおかげでこの連休の唯一の楽しみは奪われてしまった。仕方がないので家で村上春樹の新作『街とその不確かな壁』(新潮社)を読む。数週間前から読んでいるのだけれど、一向にページが進まない。少し読んではおっぽりだして……の繰り返し。村上作品でこんな経験ははじめて。とにかくこの機会に読みきってしまおうと気合いを入れてがんばる。新聞雑誌に掲載されていた書評をいくつか目にしたが、すっきりと納得させられるような内容のものは一つもなかった。ハルキストのみなさんはこの作品をどう評価しているのだろう? |
|
|
|
| 23/05/02 |
●インドの大魔王「お笑い神話(5月号)をアップしました。
|
|
|
|
23/04/28 元 正章 著 |
●元本屋人、今は牧師の元正章(はじめ・まさあき)氏による『益田っこ ありがたき不思議なり』という本を刊行いたしました。元氏にはじめてお会いしたのは、本屋人時代の、南天荘書店(神戸市)に勤務されていたころ。私どもでつくった雑誌の取り扱いをお願いすべくお店に伺ったさい親切に対応していただいた。1986年のこと。当時は、本屋人という立場だけでなく、市民団体「六甲を考える会」の代表として、八面六臂の活躍ぶりだった。それ以前には書店誌『野のしおり』の編集人もされていた。『野のしおり』はあの『本の雑誌』(1976-)のほぼ1年遅れの創刊で、活字世界にまつわるコンテンツから比較してもその充実度に遜色ない出来栄えの雑誌であった。残念ながら私が知ったのは終刊(1985)の1年後のこと。いただいた最終号(25号)を今も大切に保管している。元さんとお会いするのはたいてい飲み会の席であったが、本の世界に関係する多くの人を紹介していただいた。大恩人なのだ。聖職者になられてからもお知り合いの牧師の方による本の出版に何冊か関わらせてもらった。2017年に島根県益田市の益田教会に赴任。相変わらずのバイタリティーでさまざまな催しを立ち上げて、変わり種牧師として奮闘中である。
|
|
|
|
23/04/21 |
●インドの大魔王こと大麻豊氏より「インドの東、オディッシャ州を知る一日(講演・映画・舞踊)」の案内が届きました。5月28日京都の龍谷大学響都ホール交友会館です。詳しくはこちらのフライヤーをご覧ください。参加ご希望の方はお早めのご予約を。
●近著探訪第56回『目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 基礎知識編』をアップしました。 ●明石市立文化博物館で開催されている「写真家が捉えた昭和のこども」という写真展に行ってきた。昭和11年(1936)から昭和51年(1976)までの子どもを被写体にした写真、170点が展示されている。けっこなボリュームで見ごたえがあった。木村伊兵衛や土門拳、林忠彦などによるスナップショットがその時代性を色濃く写しとっている。薪を担いだり、稲刈りを手伝ったり、靴磨きをしたり、バナナを売り歩いたり……。社会的分業の一角にかちりと組み込まれて働く子どもたち。おしくらまんじゅうに馬跳び、ちゃんばらごっこ、コマ回し、ときには下駄で顔を殴って喧嘩をしたり。圧倒的に貧しいが、エネルギッシュで野趣にあふれる敏捷さで躍動する路上の子どもたち。小学校教員であった写真家熊谷元一の撮った、教室での子どもたちの奔放な表情は画面いっぱいに炸裂している。ほとんどがドキュメンタリーの作風の中で異彩を放っていたのはUeda-cho(植田調)と称される植田正治の演出をほどこした写真。全体の中でアクセントが利いていてよかった。来場者は70歳以上の高齢者が目立つ。フラフープに興じる子どもの写真を前にしては「腸ねん転するんよね」のお決まりのひと言、「月光仮面姿の子ども」には「げっこうかめんのおじさんは〜」と歌いだすおばあちゃんがいたり。来場者のテンションも上がり気味。賑やかな写真展であった。 |
|
|
|
| 23/04/15 |
●鶴見良行私論appendix「1970年代バンコク─井上澄夫と鶴見良行(2)」をアップしました。
|
|
|
|
| 23/04/05 | |
|
|
|
23/03/30 「納屋を焼く」 |
●鶴見良行私論appendix「1970年代バンコク─井上澄夫と鶴見良行」をアップしました。 ●アラビア語のレッスンで村上春樹作品を読んでいくことになった。1982年初出の短編で「納屋を焼く」(『蛍・納屋を焼く・その他の短編』所収、新潮文庫、1987)という作品。「納屋を焼く」ことが趣味の男と、その彼女(「僕」の女友達でもある)と「僕」の物語。男が「僕」の近在の納屋を近日中にガソリンで焼くと言う。「僕」は自宅の周辺に点在する納屋の所在を確認(4キロ四方に16ヵ所あった)し、今か今かとジョギングがてら見回りを欠かさない。しかしいつになっても納屋が焼かれたような形跡は見当たらない。そのうち男と彼女は「僕」の前から忽然と姿を消してしまい、音信不通となる。ある日、街で男を偶然見かけて声をかける。「納屋は焼きました」と彼は答えるが、細大漏らさずにチェックしてきた「僕」はそんなはずはないと思う。しかし彼は「あまりに近すぎて見落としたんですよ」と言う。彼女の消息はわからないままである。(おしまい)─うーむ、わからない。単純に村上作品でおなじみのパラレルワールドの設定かなと思ったのだけれど、「納屋」は「女」のことで「焼く」は「殺す」ことを意味しているのだなんていう解説を目にして、へぇーそうなんだと思ったり。もう一つ奇妙なことに、米国の作家、W・フォークナーに「Barn Burning」(1938)という作品があって、日本語にすると「納屋焼き」。この村上作品には「僕はコーヒー・ルームでフォークナーの短篇集を読んでいた」という下りがあってそこから読み解く解説も目にした。しかし村上本人がフォークナーの「Barn Burning」の存在すら知らなかったと述べてその関連性を完全否定しており、後年まとめられた作品集には「僕はコーヒー・ルームで週刊誌を三冊読んだ」に修正されているらしい。単純に「納屋」を英語で「バーン」、「焼く」も「バーン」だから言葉遊びから始まったのかなとも思えるし、「刺激的で面白いもの」をbarnburnerと表現することもあるらしくそこからの着想だったか!? いずれにせよ謎の多い作品であるのだけれど、これがアラビア語に翻訳されていたということ自体、これまた不思議な感じ。 |
|
|
|
| 23/03/22 | ●インドの大魔王こと大麻豊氏よりインド哲学の講演案内が届きました。参加ご希望の方はお早めにご予約ください。詳しくはこちらのフライヤー(PDF)まで。 ・演題:飯高淑子氏「印度哲学へのいざない─人間の苦悩からの解放・ドゥッカー」 ・4月29日(土)14:00〜16:00 ・西天満地域福祉センター |
|
|
|
| 23/03/14 | ●酒造好適米として有名な高級ブランド「山田錦」。その発祥の地、兵庫県三木市吉川町で「山田錦まつり」が先週末開催されていたので出かけた。日本酒メーカー11社がそれぞれブースを出して山田錦で造った純米酒、吟醸酒を試飲させてくれる。50mlほどの小さなカップ1杯が100円〜500円。近年の日本酒は高級化路線でどちらかといえばワイン風に嗜むのが流行り。ボトルも一升瓶などではなく、四合瓶(720ml)が主流だ。テーブルの上に置いても邪魔にならないしね。聞くところによると一升瓶サイズの流通量が激減し、早晩この瓶のリサイクルシステムが成り立たなくなるかもしれないといわれている。私は昔人間なので、醸造用アルコール添加の、いわゆる「アル添」の、本醸造酒あたりの品質のものを一升瓶で買って燗酒で飲むほうが好みなのだけれど、こういう一昔前の飲用スタイルは希少になった。精米歩合の数字を競うような時代で、磨きに磨いて生まれるその吟醸香とフルーティな風味をもつ、高級な吟醸酒が人気だ。きりりと冷やしていただく。もちろんこちらも大好きです。一つ違いの従兄が小さな蔵元をやっているのだけれど、彼が家業を継ぐために東京・北区にあった国立醸造試験所(現在は東広島市に移っている)で研修を受けていたときのこと。1980年ごろだ。深夜、彼の手引きで薄暗い実験室に忍び込ませてもらった(今では考えられないほどのセキュリティですね)。そこには試験中の吟醸酒が巨大なガラス瓶に詰められて鎮座していた。その瓶から実験用の小型ビーカーに恐る恐る移し替えて失敬したその一杯は、とても日本酒とは思えない、衝撃的な味わいだった。これが日本酒か!? 「吟醸」なんて言葉も知らなかった。さっぱりした白ワインのような飲みやすさで、わが背徳的行為とも相まって、その甘美さが際だって感じられたものだ。時代はほどなくバブル経済に突入し、奢侈な世相とともに90年前後には市場でも一般的になった。あれから40年超が経過して、昨今は世に知られていない小さな蔵元の、一期一会の希少性の高い逸品がもてはやされる。その意味ではこのたびの「山田錦まつり」参加各社は、灘五郷の大手蔵元の揃い踏みで、間違いのない酒造りでいいのだけれど、ちょっと面白みに欠ける印象であった。北陸から参加されていた蔵元が1社あったので珍しさもありそちらを自家消費用に購入。希少性といえば、会場の片隅で催されていた小規模な古本市(町内のメンバーで持ち寄りましたといった風情)で、ここんところ何カ月も探していた、竹西寛子『管絃祭』を発見。函入クロス装丁の新潮社版。1978年発行。100円だった。「山田錦まつり」で最高の掘り出し物に出合えた。お酒ではなかったけれど。 |
|
|
|
| 23/03/02 | ●大阪自由大学通信(3月号)をアップしました。 ●インドの大魔王「お笑い神話(3月号)をアップしました。 |
|
|
|
| 23/02/27 | ●鶴見良行私論第Ⅳ部「ベトナムからの手紙」をアップしました。 |
|
|
|
| 23/02/17 | ●たまたま手元にあった岩波書店のPR誌『図書』を眺めていたら「大流行による惨劇から一〇〇年」と題した、田代眞人(ウイルス学)という方による「スペイン・インフルエンザ」の記事が掲載されていた。1918年から19、20年にかけて猛威を振るった、このインフルエンザの世界的流行(スペイン風邪)では、当時の世界人口の3分の1にあたる、約20億人が感染し、死者は2千万人とも1億人ともいわれ、正確なところはわかっていない。というのも第一次世界大戦の最中で、参戦国の感染事情は秘匿され、そのため当時中立国であったスペインからの感染状況が悪目立ちしてしまい、「スペイン」というありがたくない冠がついてしまったという話をどこかで読んだ。さて、この記事で紹介されている、パンデミック下の世界大戦にまつわるいくつかのエピソードと、その後の歴史への影響を述べたくだりが興味深かった。連合国・同盟国ともに戦力の消耗は激しく(戦死者1000万人に対して参戦国のインフルエンザによる死者数はそれ以上)、「パリに迫る西部戦線では、ロシア戦線から戦力を転用したドイツ軍の最終攻撃は中止」され、「それがドイツ降伏の原因ともいわれる」。パリ講和会議では、ドイツへの賠償金請求をめぐって、強硬派のフランスと、穏健派の米国ウイルソン大統領が対立。会議中にウイルソンと英国の首相ロイド・ジョージがインフルエンザに感染してしまう。一命を取り留めたウイルソンは、「精神神経症状を呈して思考・意欲が低下し、病床でフランスによる強硬な講和条約案に無気力の状態でサインしたと伝えられている」。結果、巨額な賠償金を課されたドイツの経済は破綻し、世界はパンデミックによる労働力不足で経済復興もままならず、ほどなく大恐慌に突入してゆく。疲弊した民衆はファシズムの台頭を許し、その流れは第二次大戦へと向かい、さらにその延長線上には、アウシュビッツや、沖縄・広島・長崎などの惨事が歴史に刻まれていくこととなった、と述べる。歴史への負の刻印である。かつてヨーロッパを席巻した黒死病(ペスト)はその中世を終わらせ、近代の幕開けへと繋げたといわれる。これなどは肯定的な評価でもって捉えられるパンデミックの刻印といえるかもしれない。はたしてこのたびのコロナ・パンデミックからはどんな歴史が紡ぎだされ、そして将来どのような刻印がなされるのか……。残念ながら記事には、そうした論考はなく、コロナの「コ」の字も言及がなかった。あれれっと表紙を見直すと、それもそのはず、これは、な、なんと2019年2月号の『図書』であった。コロナ禍勃発のちょうど1年前の刊行である。記事の後段は、「スペイン・インフルエンザを超える最悪のパンデミックの発生は時間の問題」と警鐘を鳴らす、インフルエンザ学者R・ウェブスターの自伝的著書『インフルエンザ・ハンター ウイルスの秘密解明への100年』(新刊、岩波書店)の一読をすすめるものであった。「ウイルスの驚異的な存在様式、将来への教訓と問題提起」が平易に解説されている由。厚労省の関係者や、感染症対策専門家会議のみなさんは、これ、読んでくれていたかなあ? |
|
|
|
| 23/02/11 | ●鶴見良行私論第Ⅳ部「サイゴンの6日間」(1)をアップしました。 |
|
|
|
| 23/02/03 | ●大阪自由大学通信(2月号)をアップしました。 ●インドの大魔王「お笑い神話(2月号)をアップしました。 |
|
|
|
| 23/01/25 | ●メインにしているパソコンがついにうんともすんとも言わなくなってしまった。ここ数年起動にさいして、ふつうには立ち上がってはくれない状態にあった。いったんコンセントを抜いて、数十秒間電源を完全にシャットアウトしておいてからコンセントを挿しなおし、さらにそのまま数時間放置させたのち、おもむろに電源ボタンを押すと立ち上がってくれた。すでにかなりいかれていたのである。それがまったくの無反応になってしまったのだ。ついに来てしまった! 幸い、同じOS環境の機械をほかに2台用意していたので急場はしのげる。だけどメイン機に比べると、サクサクした動きに欠けるところがあって、作業効率がぐんと落ちてしまう。ストレスフルである。悩みに悩んだすえ、PC店の修理窓口に持ち込んだ。2002年発売のPowerMac G4(MDD)だから20年以上使ってきたことになる。当然使われている部品やユニットの製造はとっくの昔に終了しており、中古機から部品どりしたものを組み込むしかない。Win関係の修理費用は明細ごとに掲示されていて明朗会計だが、Apple社製にかんしては応相談というやつ。部品にしても時価となっていて、言い値を受け入れざるを得ない。結局、電源ユニットを交換し、2枚装備していたハードディスク(HDD)も交換となった。HDDの一つはパーティションを切って2区画にOSをそれぞれインストールしていたのであるがそれもそのまま復元。ほか筐体内の積もりに積もった20年間の埃をきれいに落としてもらい、データもアプリも完全移行してもらった。新品の小さなコンピュータが買えるくらいの費用になってしまったが、よみがえってくれた機械を前にして喜びのほうが大きい。この環境でないと、DTP関連のソフトや周辺機器が動いてくれないのだから仕方ないのだ。お店の女性が「これからも長く使えますよ」と送り出してくれた。さらにもう20年行けるであろうか。いやいやこっちの寿命を心配しなきゃならないな。 |
|
|
|
| 23/01/19 | ●近著探訪第55回『天路の旅人』をアップしました。 |
|
|
|
| 23/01/07 | ●大阪自由大学通信(1月号)をアップしました。 ●インドの大魔王「お笑い神話(1月号)をアップしました。 |
|
|
|
| 23/01/02 |
●あけましておめでとうございます。本年もおつき合いのほどよろしくお願い申しあげます。 ●アラビア語のレッスンで昨夏より読み始めたガッサーン・カナファーニーの「オレンジの大地」も昨年末でようやく最終の数行を残すのみとなった。日本語版にしてわずか8頁ほどの短編を半年かけて読んできたことになる。発見だったのは、あちらの文章の特徴なのか、ひとつの文が何行にもわたってとてつもなく長いことだ。日本語だったらそこに三つ四つの句点を入れるべしと指導が入りそうなほど。文章のあとをカンマで区切って、そのあとに分詞構文で状況説明文をいくつもいくつも連ねていく。訳しているうちにもともとの主節が遠くにかすんでしまって、言いたかったことはなんだったの?ってな具合になってしまう。贅肉を削ぎ落とし簡潔を旨とする日本語とは真逆の、デコラティブで過剰で粘着性の文章が名文と賞されるのだろうか。先生によると、フランス語もそのような傾向があって、「ル・モンド紙」の記事なども一文がくねくねとしてとても長いそうだ。そのことがインテリの文章として評価される由。ユーラシア大陸の西のほうではそういった文章が好まれるのかな。湯川豊『須賀敦子を読む』(新潮文庫、2011)に、須賀の「息が長く、ゆったりしている」文章についてこう評する下りがあった。「過去という思念の中に分け入っていくのに、読点を多用して記憶をまさぐるようにどこまでも折れ曲がっていくこうした文章がふさわしい、(略)プルーストの大長編で私たちはそのことを知っている」と。須賀は31歳(1960)から41歳(1970)までのおよそ10年間をイタリアで生活し、後年60歳を過ぎて、30年以上前のイタリア時代のことを回想する作品を次々と発表して作家となった。「読点を多用して」「どこまでも折れ曲がっていく」文章スタイルが遠い昔の記憶をしるす内容にかなっていると評価するのだけれど、おそらくは、イタリア語の文章スタイルからの影響ではないかしら。プルーストだってフランス語ゆえのことではないのかなと思うのだが。 |
|
|
|
| ■2001年版■2002年版■2003〜2004年版■2005~2007年版■2008〜2009年版■2010〜2012年版 ■2013〜2014年版■2015年版■2016年版■2017〜2018年版■2019年版■2020年版■2021年版 ■2022年版■最新版 ■前世紀のWhat's NEW! はWhat's OLD!まで。 |
|
|
| お問い合わせ
|
|