 |
|||
|
「目が鍛え直され発想がふくらむ 新しい自分が生まれる」1(『アラフラ海航海記』の帯文より) 『辺境学ノート』(めこん、1988)に続くフィールドノート第2弾は『アラフラ海航海記 木造船でゆくインドネシア3000キロ』(徳間書店、1991)である。1988年の東インドネシア(アラフラ海、インドネシア語でヌサンタラ)への航海日記を書籍化したものだ。 昆虫採取を職業としたイギリス人博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォーレス(1823-1913)は、著作『マレー諸島』(ちくま学芸文庫、1993)などを書き残しているが、そのマレー諸島は、アラフラ海にある。19世紀末のウォーレスの時代、イギリス人から見れば現在の東インドネシア諸島は「マレー諸島」であった。この海域を航海した良行は、フィールドノートを「アラフラ海航海記」として本にした。良行たちと航海を共にした村井吉敬と藤林泰は、編著の論文集を『ヌサンタラ航海記』(リブロポート、1994)としている。 「マレー諸島」「アラフラ海」「ヌサンタラ」は、同じ「東インドネシア諸島海域」の異なる名称である。ヌサンタラは、インドネシア語でこの地域の「島じま」を意味する言葉として使用されてきた。いずれこのヌサンタラという呼び名がより一般化されることになるだろう。2022年1月、インドネシア政府は計画中の新首都の名称を「ヌサンタラ」として公式発表した。カリマンタン島(ボルネオ島)の東カリマンタン州に新たな首都が建設される計画だ。「島じま」の意味としても使用されてきた「ヌサンタラ」が首都名になろうとしている。 「ヌサンタラとは『島嶼地域』をあらわすインドネシア語だが、今ではヌサンタラ=インドネシアとして使われている」(村井吉敬・藤林泰編『ヌサンタラ航海記』、村井吉敬による「序文」p.8) ヌサンタラというインドネシア語の意味変容を村井吉敬や良行らは現地で体感してきた。新首都の名称がなぜヌサンタラなのか?と疑問を持つ人たちに、かれらの残したフィールドノート(航海日記)が参考になる。 現在のインドネシアの首都ジャカルタは、旧宗主国のオランダが決めた場所である。シンガポールやマラッカなど国際交易港との交易の利便性で首都の位置が選ばれてきた。しかし21世紀の多民族国家インドネシアの中心は、ジャカルタよりも北東のスラウェシ島南東部がふさわしい。そう考えたのが、現在のインドネシア政府である。国民の多数派も納得している。新首都ヌサンタラは、多民族国家インドネシアのまとまりを取り戻す首都として期待されている。 1987年の7月から9月にかけて良行たちは、ブトン島、アーネムランド、トレス海峡の旅に出かけている。ブトン島は、インドネシア領。アーネムランド、トレス海峡は、オーストラリア領にある。地図上では隣の島でも飛行場のある都市にいったん引き返しての旅となった。(「ブトン島、アーネムランド、トレス海峡の旅 南洋真珠史 アイランダーの島」『鶴見良行著作集12』Ⅲ章所収)。 「(1987年)8月29日 ウィグラム島→ケアンズ 6時半起床。(ウィグラム島のホテルで)朝食時に請求書を受けとる。総額、A$2955(日本金(ママ)で、約31万円)。村井さんと想像していた値段のほぼ倍である。この値段で水もないとあっては、ほとんど客も来まい。私が有りカネ全部のA$800、村井氏がA$2100を出して、ようやく支払う。急にカネが心細くなる。8時半、迎えのヘリで出発」(鶴見良行著作集12、p.143) 北オーストラリア、ウィグラム島などへの旅行は、現在のオーストラリア領・木曜島周辺に真珠採りに行った和歌山県出身の日本人ダイバーたちの足跡を辿る旅でもあった。この旅から帰国した1987年9月からの良行は、アラフラ海航海への準備を本格化している。東インドネシア諸島へ140トンの木造機帆船を借り切って航海するという計画に向けて動き出した。目的の島嶼地域は、これまでのエビとナマコの研究で「興味が増してきた地域」であり、「行かないと分からない」ことが多くあった。 旅の準備過程については、村井吉敬・藤林泰編著『ヌサンタラ航海記』(リブロポート、1994)の村井による序文の中に時系列でその経過が書かれている。村井によれば、1984年ごろに旅の最初の着想を得たという(村井吉敬「見果てぬ未来への夢物語」/『ヌサンタラ航海記』所収)。この着想が現実に動き出すには、いくつかの外部要因を必要とした。最初のきっかけは、イギリス人の映像作家ブレア兄弟が、ウォーレスの旅をまねてマレー諸島へ航海してつくったドキュメンタリー映画である。1987年それを村井たちはオーストラリアで見た。 「かれらの身の入れ方は私たちよりすごい」(『辺境学ノート』p.191 ) オーストラリアの村井から東京の良行に届いた手紙にはそうあった。それに対して良行が書いている。 「オーストラリア人研究者と競争する気はないが、私たちも、辺境に身を入れたいと思うのである」(『辺境学ノート』p.191) 良行がこの文章を書いたのは、1988年前半の「アラフラ海航海」へ向けた旅の準備過程である。 実施に向けて、決定的な出来事となったのは、一つにブレア兄弟に船を斡旋したウジュンパンダンの中国系貿易商が村井たちに船を貸すことを諒承したこと。1987年の旅の途上でのことだったと推測する。もう一つに、民間人からの寄付があったことだ。旅の全額を賄えるような金額ではなかったが、この地域への調査研究旅行にお金を出してくれる個人に出会えたことは、良行たちには大きな意味を持った。 そうした準備作業の中で、どんな人材で調査チームをつくるかがイメージできるようになった。エビ研究会の延長の調査旅行であり、研究リーダーの村井吉敬が隊長となることは決まっていた。村井の配偶者で共同研究者の内海愛子(恵泉女子大教員)も参加予定者となった。インドネシア語が流暢で「インドネシア人に近い人」(�「アラフラ海航海記�」まえがき)と評された福家洋介の参加も予定された。良行を含めて、この地域への調査旅行を重ねてきたこれら4人がコア・メンバーとしてチームが編成されることになる。 結果的に1988年のアラフラ海への旅は、村井・鶴見を中心に16人の日本人が参加した。船員は12人で、総計28人での航海である。乗船人数については、日本人乗客16名、インドネシア人13名という記録もある(『ヌサンタラ航海記』1994)。インドネシア人のうち1名は、良行たちの調査隊が雇用した料理人イスマイル君である。彼は、ときに船の船員としては数えられていない。もうひとり、船員ではないインドネシア人コンサードール(調整員)のアミンさんが乗り込んでいる。船会社の指示で良行たちの調査団に世話役として乗り込んだ船会社の社員である。この人物が、日本人グループを親身に援助した。役人との交渉や、船内で身勝手に振る舞う日本人たちと船員たちとの摩擦が最小限になるよう、調整役として活躍した。 小型船、16人という人数、35日間という日数(出発前の現地での準備作業を含めば40日間)、3000キロという航海距離……。本格的な学術調査団となった。そのため、計画段階では参加者をどう絞り込むかが旅の成功を左右する決定的な要因になると考えられた。十分にない真水、海に張り出した粗末なトイレ兼シャワールーム、船員たちとの共同生活。 「船尾には、二メートル四方の板囲いの真ん中に長方形の穴が開けられただけの古びたトイレ兼シャワールームがあるだけだった」(藤林泰「旅の記録『航海日誌』」/『ヌサンタラ航海記』所収、p.15、リブロポート、1994)。船上での水浴びを我慢して、船の立ち寄り先の港のホテルで水浴びした日本人参加者も少なくなかった。 事前準備の多くは、参加者各自にまかされた。参加への本気度が問われた。航海途中に立ち寄った港の郵便局から遺書のような手紙を家族に送った参加者もいたようだ。そんな気分にさせられるほどに激しい船酔いを体験したメンバーもいた。このような過酷な航海に、誰を誘い、誰を断るか。出発直前までの半年以上、人選の検討が続いた。 参加者の人選について、良行の相談相手となったひとりが、高橋久夫である。良行の�「アジア勉強会�」(1971-75)の創成期メンバーであった高橋は、1960年代末の学生運動・日大闘争を学生として経験していた。その後、独自にアジア学への道を歩みはじめている。ミャンマー、タイ、ラオスが主要な研究領域である。1971年以降、良行が亡くなるまでの20年以上、高橋はなにかにつけて良行の相談相手だった。良行が京都に移ってからも、その関係は続いた。 |
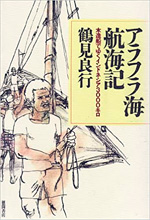 『アラフラ海航海記』 鶴見良行 著 徳間書店・1991年  『ヌサンタラ航海記』 村井吉敬・藤林泰 編 リブロポート・1994年 |
||
|
■庄野護(しょうの・まもる) 1950年徳島生まれ。中央大学中退。学生時代よりアジア各地への放浪と定住を繰り返す。1980年代前半よりバングラデシュやネパールでNGO活動に従事。1989年から96年までODA、NGOボランティアとしてスリランカの都市開発事業に関わる。帰国後、四国学院大学非常勤講師を経て、日本福祉大学大学院博士課程単位取得。パプアニューギニア、ケニアでのJICA専門家を経て、ラオス国立大学教授として現地に2年間赴任。『スリランカ学の冒険』で第13回ヨゼフ・ロゲンドルフ賞を受賞(初版)。『国際協力のフィールドワーク』(南船北馬舎)所収の論文「住民参加のスラム開発スリランカのケーススタディ」で財団法人国際協力推進協会の第19回国際協力学術奨励論文一席に入選。ほか著作として『パプアニューギニア断章』(南船北馬舎)、共著に『学び・未来・NGO NGOに携わるとは何か』(新評論)など。 |
|||