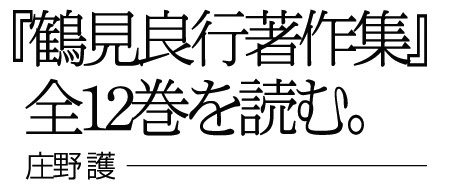 |
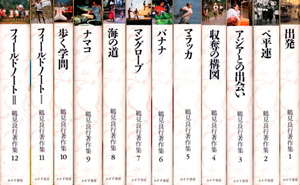 |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| 第1巻「出発」の内容を他の本で読むとすれば、日高六郎編『1960年5月19日』(岩波新書、1960)がある。鶴見良行は、Ⅳ章「ハガティ事件とアイク招待中止」を日高六郎(社会学者、1917-2018)と共に執筆している。ほかの執筆者に、藤田省三(思想史家、1927-2003)、荒瀬豊(社会学者、1930-)、石田雄(いしだたけし、政治学者、1923-2021)、鶴見俊輔(哲学者、1922-2015)など60年「安保」当時の日本を代表する知識人たちが並ぶ。 そこでの良行の作業分担が、1960年「安保」での良行の立ち位置と役割を示している。60年当時、34歳の良行は、知識人グループの事務局長的存在であった。64年からの「ベ平連」によるベトナム戦争反対運動や、70年「安保」の時代において、良行は無党派だったが(ほぼ)最前線にいた。しかし、表立って最前線に立てない事情があった。政府から助成を受ける財団法人国際文化会館の職員だったからだ。言動を控えめにしていた良行だったが、それでも73年、国際文化会館の理事を退職し、非常勤の嘱託職員となった。良行の言動が国会で取り上げられたからである。 第2巻「ベ平連」に収録されている単著は、『反権力の思想と行動』(盛田書店、1970)である。時代の雰囲気を感じるには、古本を入手し、横において読むとよいだろう。 第3巻「アジアとの出会い」に収録されているのは、『アジア人と日本人』(晶文社、1980)である。もう一冊、編著『アジアからの直言』(講談社現代新書、1974)も第3巻を読むときの参考になる。『アジアからの直言』は、良行がアジア研究者としてデビューした作品でもある。 このように第1巻から第10巻までは、対応する単著や共・編著がある。それらを古書で入手して手元に置き、著作集は図書館から借りて読むという方法がある。第11巻、第12巻の「フィールドノートⅠ、Ⅱ」に対応する単著は、『辺境学ノート』(めこん、1988)と『アラフラ海航海記 木造船でゆくインドネシア3000キロ』(徳間書店、1991)である。著作集全12巻を順番に読むよりも最初は単著で読むほうが現場の臨場感を得やすい。最終的には、両者を読み比べて良行の全体像に迫ってみるのも方法である。 各巻には、それぞれ12ページほどの「月報」がついて刊行された。執筆者の個性が文章に表れ、「月報」でしか読めない内容となっている。「月報」12回分をまとめて新書にしても面白いかもしれない。古本で著作集各巻を購入する際は、「月報」の有無について確認してほしい。「月報 第1号 1998 11・25」は、第1回配本、著作集6「バナナ」に添付されている。次の3人が寄稿者として名を連ねる。 吉岡忍「余韻のなかにたたずむ」 坂巻克己「未来に生きる仕事」 赤嶺綾子「ラオスで思うこと」 最初の執筆者・吉岡忍(1948-)は、ノンフィクション作家である。これまで20冊以上の単著がある。2017年から21年まで、日本ペンクラブの会長を務めた。ノンフィクション作家界の大御所である。吉岡が良行と出会ったのは1967年、ベトナム反戦運動(「べ平連」運動)の活動中だった。当時、吉岡は19歳の大学生。良行が大きな役割を果たした米軍脱走兵の支援活動にも吉岡は参加した。 その後の吉岡は、「ベ平連ニュース」編集長を務めるなど、運動の中核を担った。1969年、新宿西口地下広場での「新宿フォークゲリラ」集会でも活動している。74年の「ベ平連」解散後も、吉岡と良行は折にふれ会っている。93年の秋に、京都・龍谷大学の鶴見良行研究室を訪ねた時の様子が、上記「月報 第1号」の巻頭に記されている。次のような書き出しで始まる。 「『ココス島に行こうと思っているんだ』 龍谷大学の研究室を訪ねたとき、鶴見良行さんはいつもの歯切れのよい口調で、そう言った」 吉岡が鶴見俊輔と対談した本がある。『脱走兵の話 ベトナム戦争といま』(編集グループSURE、2007)である。1967年に日本の米軍基地からベトナムに派遣されることを拒否して脱走兵となった兵士たちへの支援活動が語られている。30年後でしか語れない当時の事情がそこで語られている。67年当時には活字にすることができなかった内容である。そこにも良行が何度か登場する。 脱走兵支援活動を経験した吉岡は、現実社会で「語れない世界」「書けない世界」の存在を経験した。いっぽうで、「書けない世界」の周辺に書くべき世界を見つけられるようになった。そして、「書くべき世界」を伝えるためにルポルタージュ作家となった。 吉岡忍『日本人ごっこ』(文芸春秋、1989・文春文庫、1993)という作品がある。タイで日本人のフリをして周囲の人々をだまして生きたタイ人少女の実話物語である。日本人が、タイでどんな存在だったのか理解できる。『日本人ごっこ』と良行の「日本人ばなれの生き方について」(『アジア人と日本人』晶文社、1980)は、一対の論考としてある。比較して読めば、二人の「日本人へのこだわり」が分かる。 「月報 第1号」の二人目の書き手は、坂巻克己である。『バナナと日本人 フィリピン農園と食卓のあいだ』(岩波新書、1982)を担当した編集者が、坂巻克己である。 編集者・坂巻と良行は相性が良かった。互いにビール好きであった。 「二人ともビールが大好きだから、お宅で(当時、武蔵小金井市にあった鶴見良行の住居=引用者註)昼間から、アッという間に十缶以上あけてしまったことがあった」(「月報 第1号」p.5) 岩波書店での『バナナと日本人』についての編集会議もビールが並べられていた。完成原稿前の詰めの作業では、良行は数人の若い仲間たちを編集会議に招いて原稿コピーを読ませ自由に発言させた。『アジア人と日本人』の担当編集者・津野海太郎や、津田守(大阪大学名誉教授、当時は四国学院大学専任講師)も参加していた。 「二度にわたり(中略)夕刻から深夜二時近くまで、その草稿を一枚ずつめくりながら議論した(中略)それ以前も以後も、私はそのようなことを経験していない」(「月報 第1号」p.5) 良行は、数人による編集会議のあと自宅に原稿を持ち帰って徹夜で書き直した。そして翌日、岩波書店に持参した。そのような書き直しを繰返して、『バナナと日本人』の原稿は完成した。執筆中の良行の机の上にもビールがあった。 *別稿(鶴見良行私論:文庫・新書でふりかえる「鶴見良行の世界」)を参照ください。 「月報 第1号」の3人目の執筆者は、赤嶺綾子である。「ラオスで思うこと」と題する文章が載っている。沖縄出身の赤嶺は、龍谷大学経済学部、大学院を通じて良行から直接の指導を受けた唯一の学生である。赤嶺が学部での良行の講義に出なければ大学院進学もなかった。修士論文を書き上げたあと赤嶺は博士課程に進学し、タイの国立チュラロンコーン大学に交換留学した。龍谷大学とチュラロンコーン大学とは姉妹校提携していた。良行はタイ現地に赴いて、チュラロンコーン大学の受け入れ側の職員や教員と直接交渉した。その交渉過程は、著作集12「フィールドノートⅡ」(p.294-300)に記述がある。 赤嶺はタイに留学してタイ語をマスターしただけでなく、隣国ラオスの言葉であるラオス語も旅して習得した。ここでの「習得」とは、読み書き、会話の総合力が現地の中学生の程度か、それ以上の語学力のことである。日本の外務省は、赤嶺綾子のラオス語の能力に注目し、語学専門員として外務省職員とした。そして、通常の現地留学での2年間の語学研修なしに、在ラオス日本大使館に正職員として派遣した。 赤嶺「ラオスで思うこと」の文章は、外務省職員として在ラオス日本大使館で働いていた時期に書いている。 「鶴見先生がココス島を二度目に訪れた一九九四年七月、私は九月締め切りの修士論文の仕上げに躍起になっている最中であった。論文に苦心している学生を放って指導教授がフィールドワークに出る罪悪感と、『いつまで歩けるか解らない』という研究者としての時間の制限を感じていらっしゃる中、いま思えば、先生ご自身は複雑な心境でいらしたと思う」(「月報 第1号」p.8) 赤嶺は、アジア学にまったくの素人の状態から、数年で日本の外務省がリクルートするほどの地域専門家となった。良行の指導なしに、あれほどの速度で地域専門家にはなりえなかっただろう。ラオス勤務のあと赤嶺は外務省を退職し、自分の道を歩んでいる。 以上、著作集に添えられた「月報」から著作集をどう読むかについて、私論的に記した。全12巻の読み方については、 1.既刊単行本を横に置いて読む。 2.著作集巻末の「解説」から読む。 3.著作集添付の「月報」から読む。 以上3案があることを提示しておく。本の読み方は自由であることを前提での提案である。 最後に。著作集全12巻を読む際に参考にしてほしいのは、インターネット上にある「鶴見良行文庫」(立教大学「鶴見良行文庫」)である。良行が遺した蔵書約7000冊、写真約4万枚、カード約15000枚、ノート約20冊、著書約30冊が所蔵されている。そのうち(1)蔵書、(2)写真、(3)『鶴見良行著作集全12巻』の索引が「鶴見良行文庫デジタルアーカイブス」として収録され無料公開されている。著作集を読む際に、本文に関連する写真を眺めるだけでも読書が進むだろう。人の名前や地名で検索すれば、同じ人や同じ地名が別の巻にも記述があることが分かる。特に写真には、アジアの路上の屋台で食事しながら良行本人が撮った写真が多くある。写真に表れている視線の彼方に行き着いた世界が、『ナマコの眼(まなこ)』であった。 |
||||
|
|
||||
| |1|2|3|4| | ||||
|
|
||||