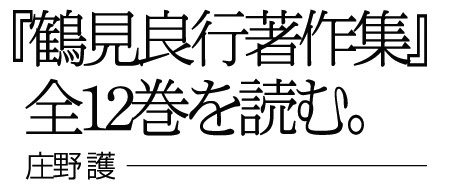 |
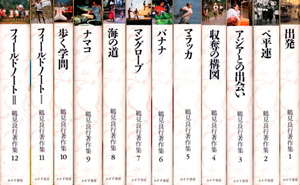 |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| 1960年代までの良行の日本社会論は、時間とエネルギーを注いだ仕事であった。代表的論文として「戦後天皇制の存在と意味」(初出『思想の科学 天皇制特集号』1962年4月号、『著作集1』p.119-129))がある。じつは、この論文が掲載された雑誌『思想の科学』は、配本直前に一度、裁断廃棄されている。 本稿では先(前回)に、 良行の単著『日本の写真』が未刊となったのは、ベトナム戦争反対運動との関わりがあった、と書いた。もう一つ、考えられるのは、この『思想の科学』裁断廃棄事件が影響していた、と追記しておく。 雑誌『思想の科学 天皇制特集号』はなぜ、刊行直前に裁断廃棄されたのか? それは、1961年2月1日に起きた「嶋中事件」(小説「風流夢譚」事件とも呼ばれる)が関係する。小説家・深沢七郎(1914-87、代表作「楢山節考」)による、皇族たちが登場する小説「風流夢譚」が雑誌『中央公論』に掲載されたことにより起きたテロ事件である。右翼の暴漢が中央公論社の嶋中鵬二社長宅に押し入り、暴漢に対応した家政婦が殺害された。 この嶋中事件の影響もあり、『思想の科学 天皇制特集号』(1962年新年号)は中央公論社社内の自主規制によって裁断廃棄されたのだった。当時、良行たち「思想の科学」同人たち(思想の科学研究会会員)は、嶋中事件を踏まえたうえで、「天皇制特集号」を企画し、執筆依頼をしていた。版元である中央公論社の編集者たちとは繰り返し話し合い、原稿内容を調整していた。それでも最終段階で中央公論社は出版を取りやめたのだった。 ところで、1961年末まで『思想の科学』が中央公論社から刊行されていたこと(1959年以降。それ以前は、先駆社、建民社、講談社と変遷してきた)を知る人はもう少ないだろう。その背景には、「思想の科学」の中心的同人であった鶴見俊輔(1922-2015)と、中央公論社社長の嶋中鵬二(1923-97)とのあいだに古い友情があったからだ。ふたりは、東京高等師範付属小学校時代の幼馴染(組み替えなしの6年間を過ごした)であった。 さて、裁断事件のあと、鶴見俊輔、良行ら「思想の科学」同人たちは自らの出版社、思想の科学社を立ち上げる。そして同じ内容で「復刊1号」を刊行した。それが、『思想の科学 天皇制特集号』1962年4月号である。 第1巻の巻末「解題」には、「第1巻は、一九四〇年代後半から執筆活動を開始した著者の、六〇年代半ばまでの前期論文・エッセイを収録する」とある(p.303)。 「一九四〇年代後半から」とは、1948年4月に22歳の良行が東京大学法学部法律学科に入学してからの執筆活動をさす。1948年7月に思想の科学研究会の会員となり、雑誌『思想の科学』の編集にも関わるようになった(『著作集12』p.427)。 『 著作集1』収録の最も古い論考は、第Ⅴ章「私の哲学 人物インタビュー1949−1950」の「岡田啓介」(題名は「安居楽住」)、「岡本太郎」(題名は「若き世代からの発言」)、「関根弘」(題名は「敗戦の裂目から」)への3編のインタビュー記録である(思想の科学研究会編「ひとびとの哲学叢書」の1冊として刊行された。『私の哲学』中央公論社、1950)。 岡田啓介(1868-1952)は元総理大臣(在職期間 1934-36)である。敗戦直後の日本では、元総理大臣が電話をかけてきた若い無名のジャーナリストを自宅に上げて、インタビューに応じた。鶴見俊輔は「今からは信じられないかもしれないが」と巻末解説で述べている(p.299)。 テープレコーダーのない時代、良行は万年筆の筆記だけでインタビュー記事を書いた。この筆記能力は特筆すべきものであった。「もし彼が、かれの父(鶴見憲=引用者註)とおなじく外交官試験をうけて、外務省に入ったら、書記として英語・日本語両方の会議録の作成に重宝され、官僚としての昇進を重ねていただろう」と鶴見俊輔は記している(p.299)。 良行による「聞き書き」3篇は、語った人物の作品としてではなく聞き書きした者の作品として『著作集1』に収録されている。そこに、特別な意味を感じる。聞き書き「岡田啓介」は、1959年刊行の『岡田啓介回願録』(毎日新聞社)に繋がっていた。本書も「聞き書き」による作品である。良行の岡田への聞き書きが、『岡田啓介回願録』を生んだといえるかもしれない。 聞き書き作品二人目は芸術家の岡本太郎(1911−96)である。岡本は戦前にパリ大学(ソルボンヌ大学)で芸術を学んだ。同時に民族学も学んでいる。画家として、彫刻家として、日本各地に作品を遺している。1970年、大阪での日本万国博覧会のお祭り広場に設置された、岡本の作品「太陽の塔」は21世紀の現在も万博記念公園に残る。 三人目の関根弘(1920−94)は、ルポルタージュや評論だけでなく、詩や小説も書いていた。おそらく良行が個人的にもっとも関心をもった人物であったろう。関根について、鶴見俊輔による『著作集1』の解説に次の文章がある。 「関根弘は、そのころ(1950年ごろ=引用者註)『思想の科学』とおなじくらい小さな雑誌『総合文化』の編集長で、当時すでに共産党員ではあったが、それ以前の戦争時代に小学校卒業だけの学歴を持つ労働者として自前でロシア語をまなび、『二人のレオーネフ』などを発表し、アナーキーな気質をもつ初期ロシアの文学者のもっていた可能性をほりおこしていた。党の制服を着ていない、じがねまるだしの共産主義者だった」(p.299) 1950年代の良行は日本共産党との距離感について考えていた。悩んでいたともいえる。旧制水戸高校時代の友人や東京大学の学友たちには、共産党員が数多くいた。彼らとの付き合い方が、共産党との距離感でもあった。そんな良行にとって、関根の生き方は参考となっただろう。 関根が残した本に『花田清輝 二十世紀の孤独者』(リブロポート、1987)がある。 ひとりで民間学をおこした花田清輝(作家・文芸評論家、1909-74)は、独自のアジア学を民間人として切り開いた良行と共通する。 関根は良行にインタビューを受けたあとに日本共産党を離党している。しかし、その後も関根は共産主義者として生きた。日本における最後の共産主義者だったかもしれない。 共産党員が共産主義者らしくなくなった20世紀の終盤、良行は過激な社会人になっていた。その生き方は、共産党を離れたあとの関根に通じる。 良行がインタビュアーとして談話構成した相手は、ほかに以下の4人がいる。 「自然に逆らわず」高浜虚子(俳人、1874-1959)、「江戸っ児の信條」三遊亭金馬(落語家、1894-1964)、「天皇陛下は大好きだ」清水昆(漫画家、1912-74)、「合理の極致」山本嘉次郎(映画監督、1902-74)。 これら4人の聞き書きは、『著作集1』には未収録である。 『私の哲学』『私の哲学 続』(思想の科学研究会編、中央公論社、1950)には全7作品が収録されている。それらをまとめて1冊の本にすることは、不可能ではないだろう。そう考えれば『著作集1』には『日本の写真』(未刊)と合わせ、良行の2冊の単著が要約されている、ともいえる。『著作集1』の総頁数は322ページで、他の巻に比べてボリューム的には少ない。しかし、未刊の2冊を想定して読むことで『著作集1』を楽しめるかもしれない。 |
||||
|
|
||||
| |1|2|3|4| | ||||
|
|
||||
 第1巻「出発」を手にとって(2)───
第1巻「出発」を手にとって(2)───