左翼の逆襲 社会破壊に屈しないための経済学 ■松尾 匡 著・講談社現代新書・2020年■ |
|
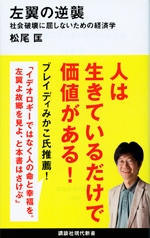
|
「拝金主義より 自分を見つめて」(朝日夕刊、2020.12.16)という見出しで中野孝次『清貧の思想』(草思社)が取り上げられていた。1992年の刊行。その3年前にバブル経済が崩壊し、経済の潮目が変わりつつあった時期である。投機やら財テクに狂奔した資本主義に決別して「われわれ祖先が作りあげた─清貧の思想─」のなかから、「新しいあるべき文明社会の原理は生まれる」と説く。ああ、あったよなあ、この本、と懐かしく記事に目を通した。あの当時、つまり90年前半は、経済的に落ち込んだとはいえ社会にはまだまだ余力はあった。記事は、文芸評論家の斎藤美奈子氏による、現時点からの『清貧の思想』に対する批評を紹介している。曰く「バブル崩壊期の典雅な寝言」「拝金主義に眉をひそめていられるのは、やはり『豊かな時代』だからなのだ」と、とりつく島もなくぶった切っている。ほんとうにそのとおりだと思う。 1990年代前半以降、経済はデフレ懸念の状況をさまよい、97年に消費税の増税(3%→5%)を機にデフレ基調へとしっかりと舵がきられ、今に至る長期低迷の起点となった。さらに2014年に再び消費税の税率がアップ(5%→8%)されて、デフレは完全に固定化されてしまう。もうじゅうぶんに青息吐息の状態であるにもかかわらず、おかまいなしに19年10月に再度のアップ(8%→10%)を決行。当年度第3四半期(10-12月)の実質GDPを前年比年率換算でマイナス7.1%と記録的に落ち込ませてしまい、さらに間の悪いことに、年が明けて20年前半からはコロナ禍に見舞われ、周知のとおり日本経済は瀕死の状態である。 需給ギャップが58兆円(2020年4-6月)ともいわれ1980年以降過去最悪の状態らしい。巨額な需要不足に対して、とりあえず打つべき手は、いの一番に消費税の撤廃しかありえないと思うけれど、この4月から商品価格の税込み総額表示が義務化されることは決定済みで、その見直しの兆しも見れらない現在、ほぼ絶望的である。 このたび松尾匡『左翼の逆襲』(講談社現代新書、2020年)を読んで、ああそういうことだったのかと初っぱなに気づかされたことは、いま直面しているどうしようもなく劣化してしまった経済状況について、私たちが取り組まなければならない問題の所在は変わってしまったということだった。それは、経済学的知見からの「傾向と対策」を論じる段階は終わったということ。つまりは新自由主義やら、リフレ策やら、緊縮・反緊縮、MMTなどなどの理論やらロジックの、これまでの是々非々をすべて前提とした上で、政財界の支配層にあるエリートたちはこれからの進むべき方向について、すでに確信的に決定済みということだった。経済学的論点を云々するステージではもうないということである。 このコロナ禍を奇貨として、ゾンビ企業を淘汰し、生産性の低い産業分野は国内生産から撤退(消滅)させて、効率よく海外からの調達に切り替え、そのためには円の価値を高く揺ぎないものにすべくプライマリーバランス(PB)を早急に黒字化し、将来にわたって高付加価値を追求できるグローバルな産業部門へ集中的におカネを投下していく。こうした方向が政策決定者側の、有無を言わせぬ大前提になっているということだった。昨秋このコロナ禍の真っ直中に麻生財務相から2025年までにPBの黒字化を目指す(20.11.19)というコメントが発表されて、心底「あほちゃう?」と思ったが、賢愚は別として、とりあえずは本気なのだということはわかった。そこにはデフレや需要不足を克服するための経世済民的な視点はまったくもってない。少子化に歯止めがきかない国内市場などはとっくの昔に見限ってしまっているということだ。国内需要をいかに喚起するかなんてことは端から視野にはない。需要側や中小零細企業に配慮するような経済政策は出し惜しみ、大企業を中心とした供給側に重心のかかった政策しか想定されていない。当然消費税を軽減するなんてことも考えない。相対的貧困率の悪化が問題視されているが、経済格差の是正なんて世迷い言となる。これからは地域帝国主義的にグローバル企業で海外から稼いでゆく。これが人口減少時代の、淘汰路線を公言する管政権が主導する「政財界の合理的な大方針」というわけだった。そして問われているのは、この方針に乗るのか乗らないのか。その分岐点に私たちは今まさにあるのだということ。そして、「ほんまにそんなんでええのん!?」ということだ。 著者の主張は、書名どおり「左翼の逆襲」の提言だ。しかしこの「左翼」の様態にはいくつかのフェーズがある。ひと昔の前の、1960年から70年代の左翼(これを著者は「レフト1.0」と呼ぶ)とは打って変わって、今の左翼は「経済」を語らない(あるいは語れない、あるいは語りたくない)。左翼という言い方も一般的ではなく、「左派リベラル」(「レフト2.0」と呼ぶ)なんていうほうが最近では通りがいい。レフト1.0の左翼が、社会主義革命を目指さないまでも、私たちの眼前に出現しているのは階級社会であるとみなし、労働者の経済的豊かさを追求する労働組合運動が中心課題であったのに対し、レフト2.0においてはそもそも労働者という主体は消え去っている。労働生産現場からは遠ざかって、反生産主義的ですらある。主体は「市民」と呼ばれるようになる。「女性、障碍者、LGBTといったマイノリティとの共生とか、承認とか、多様性とかいったアイデンティティ・ポリティクス」に焦点が移り、市民運動やNPOなどによる相互扶助的な共同体主義やコミュニタリズムが中心課題となっていく。そもそも経済は成長し続けなければならないか?という問いかけが当然のようになされ、「経済を拡大させる必要もない、景気対策もしないほうがいい」という、これまでの「成果をぞんざいに扱う」物言いでこの長期不況下に生み出されてきた多くの非正規労働者や、貧困者、生活困窮者への目配りを怠ってきた。すくなくとも逆進性において大いに問題が指摘されている消費税に関して声をあげている左派リベラルと称される方は寡聞にして存じあげない。 現下において求められるのは、頼りにならないレフト2.0からレフト3.0への移行である。「『収奪者を収奪せよ』という哲学への回帰」と著者は提言する。レフト1.0への回帰こそがレフト3.0の進むべき道であるとする。やりたい放題のリヴァイアサンそのもののと化した国家権力に対して、ついにロック由来の抵抗権の実力行使だ!と、すこし胸が躍ったのだけれど、さすがにそういうわけにもいかない。著者も「大声で言いたい気もするけれど、そうもいきません。というわけで、現代的な解釈、理由づけが必要になる」と述べて、企業や資本家が生身の個人の命と自由をどの程度毀損してしまっているか、そこへの賠償保険料的な考え方で「収奪」を説く。 具体的な手法は課税のしくみのあり方になってくるのだが、一個人の人生への影響力(コントロール)の多寡によってその負担額を決定していくことを求める。組織や富裕層は、その行使する影響力は当然累積的に大きくなってくるので、これまで必要以上に下げてきた法人税をきちんと高くすることや、所得に応じたメリハリの効いた累進課税というシステムが正当化されるという理屈になっている(課税・再分配正当化論理)。換言すれば、今とられている施策を真逆にせよということだ。著者は「ここには共同体主義的な同胞助け合い論理は一切必要ない」ということをあえて強調して付言している。 「コントロールできない勝手な意思のために被害を受けるのは不当だという、『生身の個人』を主人公にした疎外論、そしてそれと対になる、自由な意思決定の裏には責任がともなうという理性的個人の側の責任論、徹頭徹尾こうした個人主義的な立場だけから正当化理論」を導いていると結んでいる。 2021.1.11(か) |
| ■■■近著探訪(51)へ■■■ |
■■■近著探訪(53)へ■■■
|
| Copyright(C) by Nansenhokubasha Publications. All rights reserved.■南船北馬舎 | |